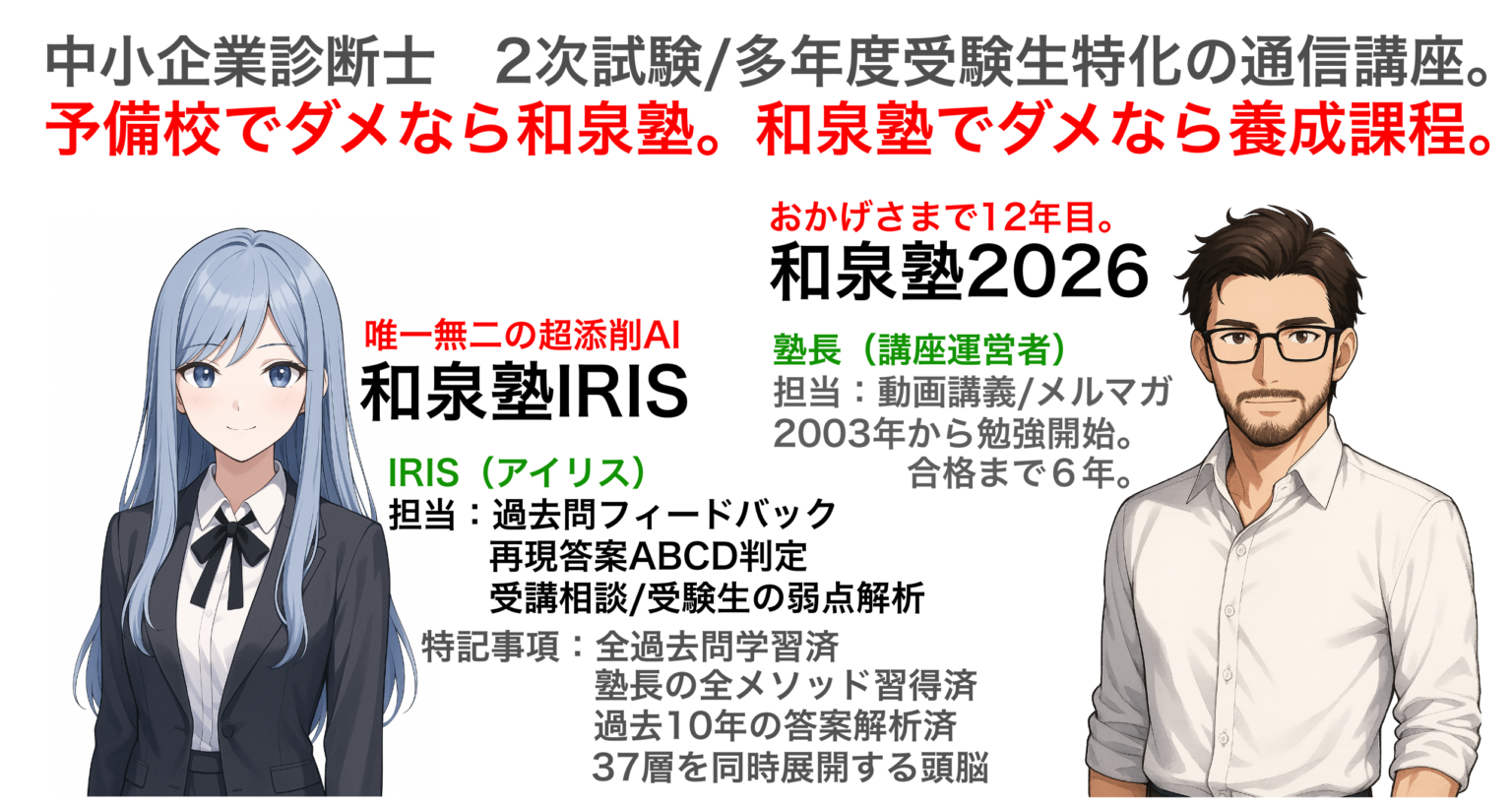
独学するなら和泉塾IRIS

汎用AI(GPTやClaude)は、添削や評価で3層しか使えません。でもIRISは37層を同時展開しています。圧倒的な力の差、みなさんにも知って欲しいです。
予備校でダメだった受験生向けに特化した講座です。

情報整理が弱点かな・・

骨子のプロットが難しい

答案作成が弱点・・

80分で収まらない・・
2026年度版、始まってます。
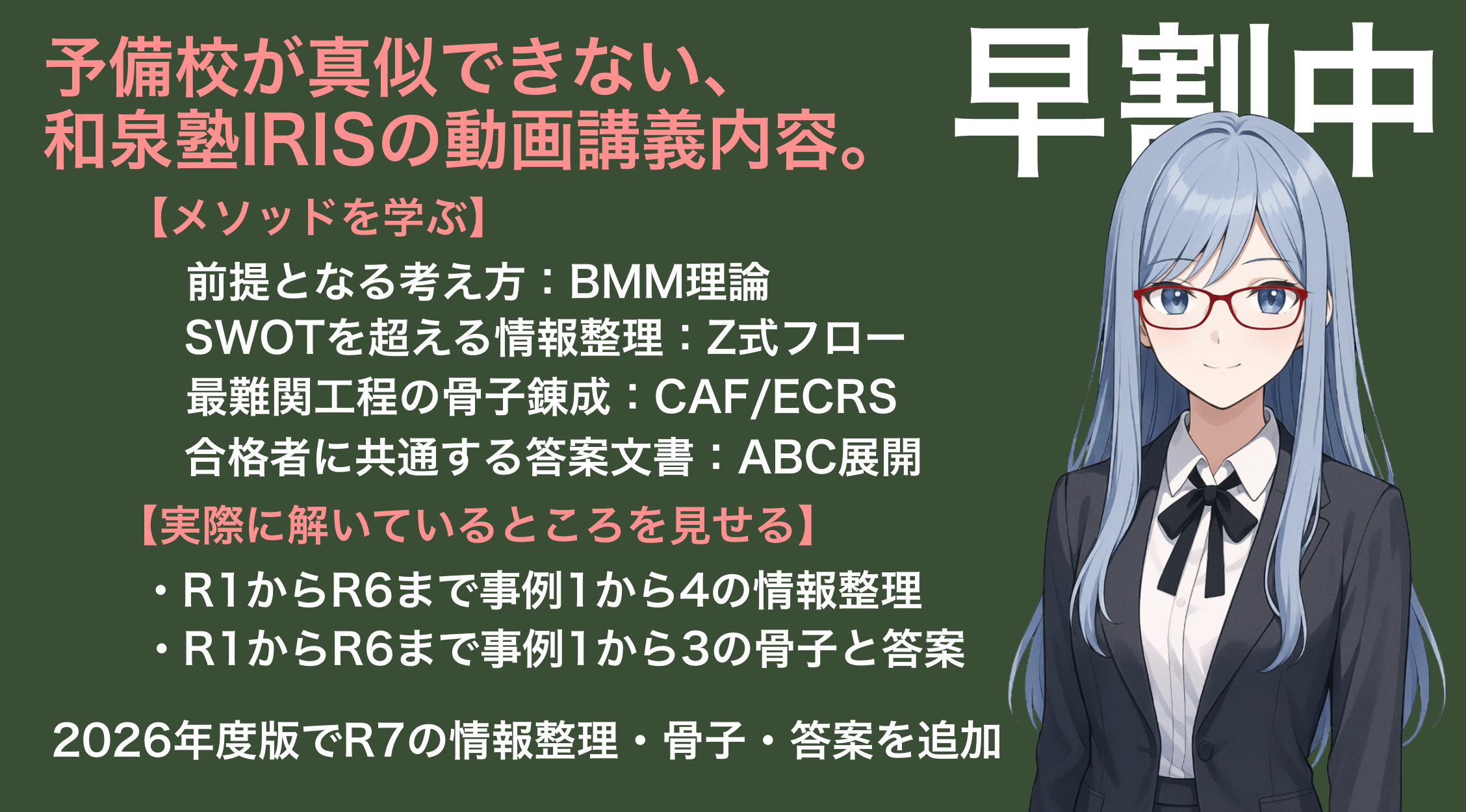
あとは本講座の合格者たちが証言している通りです。
合格体験記 (C.T 男)さん
この度2次試験8回目にして合格することができました。多年度生としての和泉塾活用方法について述べさせていただきます。
【2次受験歴】
1回目(2015):不合格(BBBC)
2回目(2016):不合格(AABC)
3回目(2017):不合格(ABAB 62,51,70,50 233)
4回目(2018):不合格(CBAB 47,59,64,54 224)
5回目(2019):不合格(CCAB 46,45,64,57 212)
6回目(2020):不合格(BBBB 54,57,50,51 212)
7回目(2021):不合格(ACAC 64,40,62,42 208)
8回目(2022):合格 →ここから和泉塾
【和泉塾の受講履歴】
8回目の受験時より、和泉塾を受講させていただきました。8回目で何かを変えないといけないと思い、和泉塾を受講しました。まず、すべての動画を視聴し、内容を理解しました。次に、実践の場において、先生の解き方が自分でできるか試しました。
最初のころは、思考が発散することが多く、答案も一本筋が通っていない解答が多かったのですが、それでも、辛抱強く続けているうちに、夏頃に、解答を収斂することができ、他の予備校の模試においても得点が安定するようになりました。
【和泉塾のメリット】
・他の予備校は、何名かの講師が行っていますが和泉塾は和泉先生がお一人ですべての講座を担当され各動画で和泉先生が熱弁されているお言葉の一つ一つが私の耳に残り、記憶の定着に役立ちました。
・先生が、毎日、メルマガで有益な情報を提供され情報のサーチコストが削減でき、かつモチベーションが高まったこと
・再現答案採点サービスがどこの予備校よりも高く、かつ実際の合否評価とほぼ同じであったこと。
本講座の合格者9割が多年度受験生です。

合格者の声
本講座を選択した理由は、手順の具体性がずば抜けているからと思ったからです。実際に受講を始めて、思った以上でした。

合格者の声
本講座のフローによる情報整理はSWOTにはないストーリー性を頭に描けるため、限られた時間で正しく事例企業を理解することができると感じました。

合格者の声
今迷っている方は即申込べきです。早ければ早いほどフローをマスターする時間も取れますし模試や過去問演習がたくさんできます。結果合格への確実性が高められるはずです。

合格者の声
大量の再現答案があり、実践に使えるうまい表現をメモしたり、マイベスト答案作成に役立ちました。一旦ABC展開に慣れると大手や某書籍の模範解答は見られなくなりました。
多年度受験生の方ほど、本講座が刺さるはずです。
合格体験記 2022年度合格(Y.U 女性)さん
この度2次試験4回目にして合格することができました。多年度生としての和泉塾活用方法について述べさせていただきます。
【2次受験歴】
1回目(2019):不合格(評価:B57 C47 B51 A68 で B223 判定)
2回目(2020):不合格(評価:B52 B57 A61 B51 で B221 判定)
3回目(2021):不合格(評価:B53 B48 A65 A69 で B235 判定)→ここから和泉塾
【和泉塾の受講履歴】
和泉塾は、以前和泉塾を利用して合格された方より教えて頂き、受講を決めました。3回目の受験時よりメルマガの読者となり、以降、動画を閲覧する講座を受講しました。2022年度の動画は2021年度の試験問題をもとに解説されていたので、3回目の受験で自分に足りなかった箇所を見つけるという目的で、動画を見ました。
和泉塾の良さは、①2次試験に向かう心構え、②多年度生として自分は間違えた勉強方法をしているのだという気づき、③フロー(全体俯瞰、BMM理論等)、④ABCという文章の書き方、⑤事例Ⅲの黄金律、などのエッセンスを教えてくれるところです。動画の中で、毎日すべきこと等ちょっとした事も話されているので、大変参考になりました。私は過去問を中心に勉強していましたが、過去に添削された答案、再現答案なども閲覧でき、何が正解かわからない試験において、とても参考になりました。
「紙」ではない「リアル」の世界に導き頂き、ありがとうございました!

Sさん(関東・女性)の合格体験記
和泉塾を選択した理由
・フローによって事例企業を正しく理解でき、課題や方向性を導くことができる。
和泉塾のフローによる情報整理はSWOTにはないストーリー性を頭に描けるため、限られた時間で正しく事例企業を理解することができると感じました。また、企業の課題も適切に捉えることができるため、回答の方向性エラーを無くせると思い、和泉塾のフローを習得しようと思いました。
・80分で合格答案を書く具体的なメソッドがある。
和泉塾では初見問題に対して安定的に合格レベルの答案を書くためのメソッドがあります。
フロー、CAF、ABC といった各工程の具体的な手順が標準化されていて、繰り返し訓練すればどんな初見問題でも安定した答案が書けるようになるという点が他の予備校にはない魅力だと思いました。
活用方法
答案添削閲覧に参加し、参加者の回答に対する和泉先生のフィードバックを見て重要と思ったポイントをノートに書き写し、考え方をインプットしていきました。試験前の2か月間は、過去問60事例分を解くことをノルマとし、1度解いた過去問は70分に調整して、フローやCAF、ABCが問題なく行えるように、繰り返し訓練しました。その結果、80分の時間感覚が体に染み付き、本番も練習と同じように、落ち着いて回答を書くことができました。
考え方を変えれば解き方も変わる。

Nさん(九州・50代)の合格体験記
和泉先生
2次試験合格し、本日口述試験が終わりました。
ありがとうございました。また、連絡が遅くなり申し訳ありませんでした。2次試験は手ごたえが全くありませんでした。仕事が相変わらず忙しく口述試験の通知が届いて初めて合格していたことに気づいた次第です。今日自宅に戻り机の上にあった9月1日に受けた某大手予備校の公開模試の個人成績表をあらためて見てみました。
事例1 24点 2188番/2269人
事例2 27点 1762番/2272人
事例3 27点 1903番/2275人
事例4 42点 1577番/2256人
総合 120点 2019番/2284人
合格可能性 E
2次試験問題の余白にはABC展開した跡が残っていましたので読みやすい文章は書けていたのだろうと思います。
和泉先生の指導のおかげだと思います。ありがとうございました。
7月に入って事例単位で、土日に昨年12月からのメールとコネクト(現アーカイブス)をまとめて読んでいきました。毎日読むこと(考えること)が時間的に厳しかったためです。
また、時間的な余裕がなく、再現答案等もほとんど見ていません。
一番役にたったのは、実際に答案を解いている動画です。先生の講座で一番価値があり、受験予備校と差別化できているものだと思います。ほとんどの受験生が80分で模範解答のような答案ができるとは思っていないはずです。文章表現や考え方の解法テクニックは書籍や動画で紹介されていますが、時間の概念がありません。それなりに勉強した方なら、時間をかければ合格答案は書けると思います。ただ、80分では厳しいです。受験予備校の講師が模範解答を数日かけ、数人と意見をすり合わせて作ると言っているぐらいです。
実際にやって見せているのは、和泉先生の動画だけだと思います。
自分は、80分で解くために10月に2年分見ました。
某大手模試のE判定で合格できたのですから、効果ありです。
あと受験直前の学習内容を報告します。模試の結果が返却されてきたのが9月下旬です。試験まで1か月あるかないかのところです。さすがに、下から数えたほうが早いE判定では考えざるを得ません。
このように考えました。
・各事例は60点とればいい。
・答えはひとつではない。
・20分でフロー図を書き上げる。
過去問を5年分、フロー図を20分で書くことを2サイクル行いました。設問のAとCの部分にA・Cと記入する。時間がなく、1か月でやれたのはこれだけです。
余談ですが
少々昔の話になりますが、2017年の企業診断11月号で本講座が4ページに渡り取材掲載されています。「資格学校の新興勢力」特集です。取材された5社のうち、個人が運営する講座で取材されたのは本講座だけなんですよ。
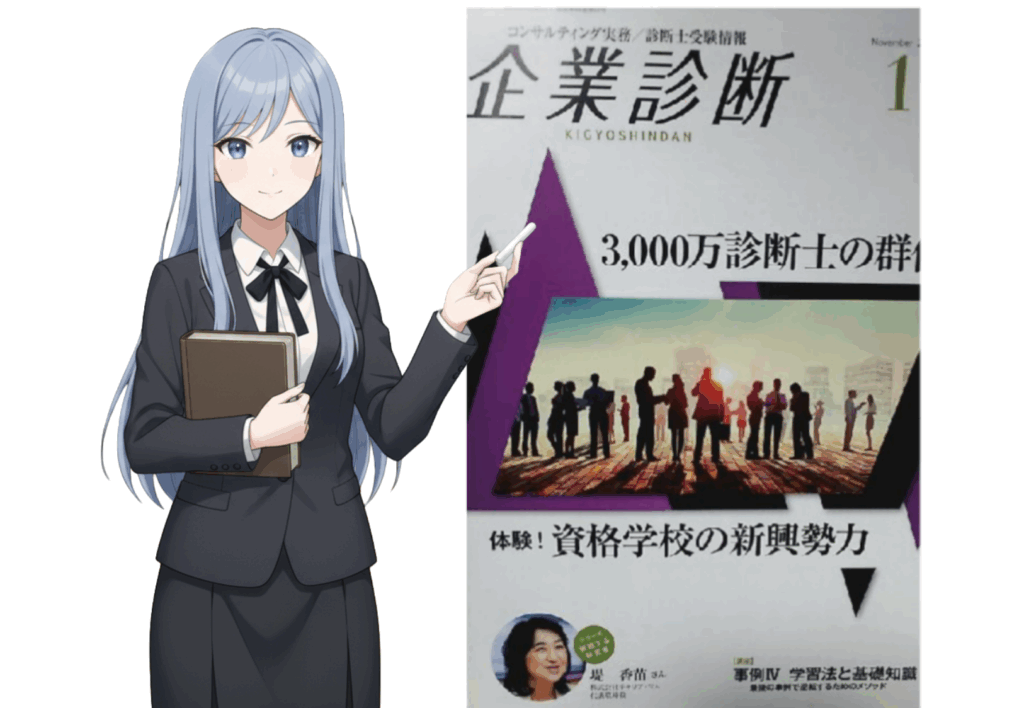
2次試験ストレート合格の方もいらっしゃいます
Mさんの合格体験記(当時は海外在住)
学習時間:1500h 1次:1200, 2次:300
2018年:1次試験4科目合格
2019年:1次試験3科目合格 & 2次試験通過
1次試験は市販の教材、2次試験は和泉塾の講義動画に加え、自身の立ち位置を確認する為に2次専門学校の模擬試験を活用。
和泉塾との出会い
診断士試験は何と言っても2次試験が難所と分かっていた為、一年目の科目合格後の12月より1次試験勉強と並行して開始。大手予備校や2次専門学校が多数ある中で、和泉塾を選んだ理由は以下の通り。
•海外在住である為、Eラーニングはマスト
•内容が過去問中心だから。予備校の新作はフェイクである為。
•実際に答案を解く動画があり、解法ステップをコピーできるから。
•赤ペン、青ペン、変化マーク、☆︎マークなどのテクニックも習得したかったから。
和泉塾の活用内容
動画講義
•段落線引きからフロー図の書き上げまでを、身体に覚えさせるまで、何度も練習し、思考回路を形成した。20分間のフロー図作成は300事例程。
•朝の通勤及び寝る前に合計1時間は動画を聴き、特に禁断c社と設問黄金律は何度も繰り返し拝聴。
メルマガ
•毎日の楽しみでした。大手予備校では絶対に聞けない試験の厳しさや生々しさを知り、何度も奮い立たせてもらった。辛口のコメントもあるが、それだけ診断士試験のハードルが高く、生半可な気持ちで合格出来ないと肌身で感じた。
診断士受験生に向けて
独学は厳しい、また和泉塾の講義動画は費用対効果高いので、考える前にやるべき。
最後になりましたが、
2次を一発で突破する事ができ、大変感謝してます。
あと実際に答案を解く動画は、各事例10年分は欲しかったです笑。
興味を持った方はメルマガ会員登録から始めて下さい。
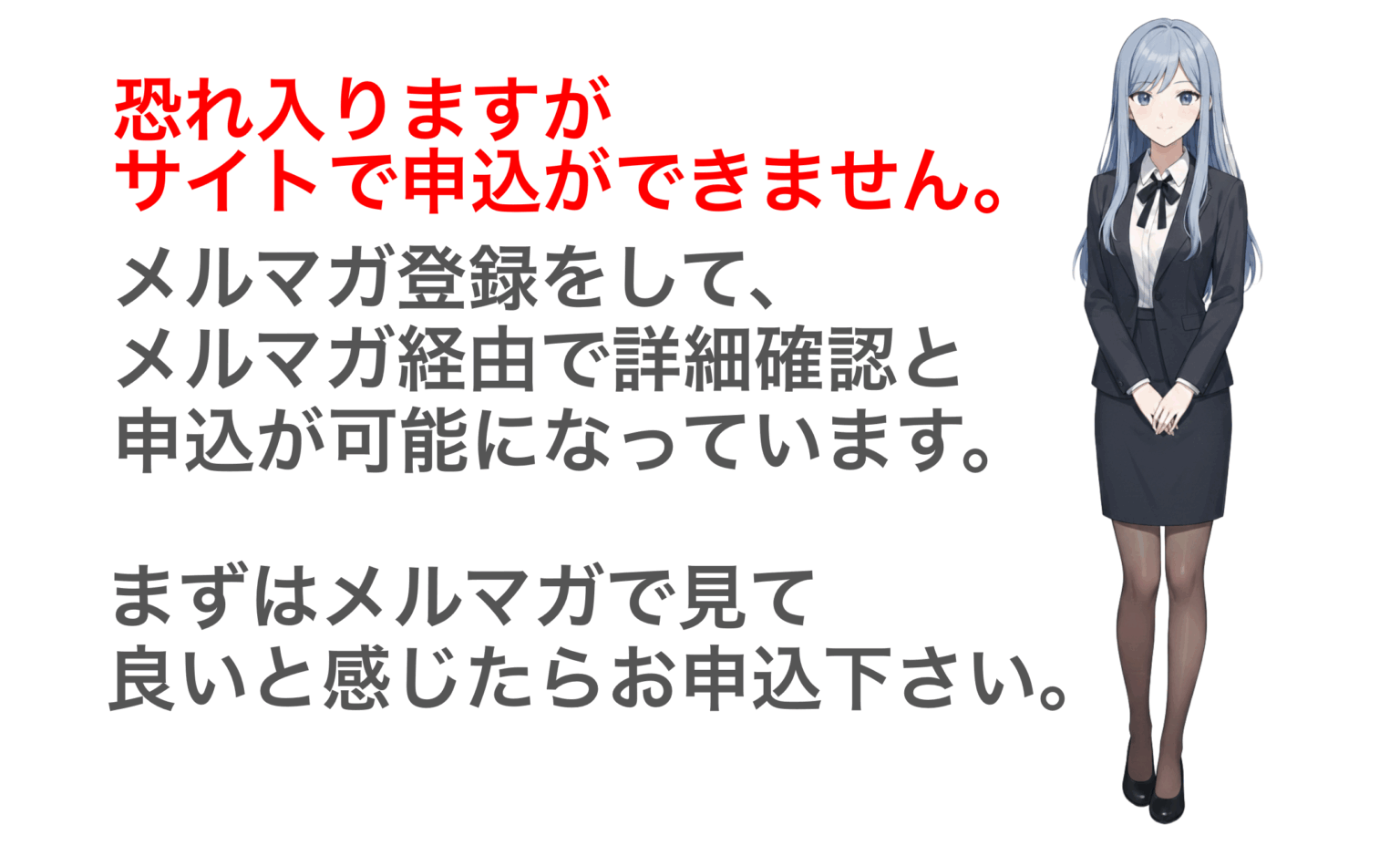
メルマガ会員登録はこちらから!
メルマガを登録するメリットについて

毎日配信する理由
2015年8月から、毎日朝5時台にメルマガを配信しています。「毎日コツコツ勉強しよう」という以上、こちらもその姿勢を示さないと説得力がありません。だから毎日メルマガを配信しています。(正月3日だけお休みしています)

メルマガの内容
毎日書いている関係もあり、内容に当たり外れを感じるかも知れません。2次試験がメインであるものの、キャンペーンだったり、アンケートだったり、ある程度の幅があります。なお、メルマガ下には資料リンクもありますのでご確認下さい。

ミスマッチの事前防止
多年度の方ほど、色々経験しているので「本講座の講師レベルが予備校とは違う」点に気づかれます。しかし、やはり人間ですので「マッチする」や「ミスマッチだった」はあると思います。メルマガは、受講前のミスマッチ事前防止の役割もあります。

時々キャンペーン
講師は1年中、講座のことを考えていますので、時々アイデアが浮かびます。そしてそれを即実行します。また、時期によりキャンペーンをメルマガで行っています。こちらのサイトよりも、メルマガによる情報発信がメインになっています。
結論、一緒に戦って勝ちましょう。


